規範と制度
アテンション・エコノミーと「情報的健康」
現在の情報空間は、個人のアテンション(関心、注意)や時間が交換財として取引される「アテンション・エコノミー」と呼ばれるビジネスモデルに支配されていると言われる。そこではAIが、可能な限り多くのアテンションを私たちから奪うため、大量の個人データからユーザーの属性や認知傾向を予測・分析(プロファイリング)し、そのユーザーを最も強く刺激できる情報・コンテンツをレコメンドするために使われている。こうしたAI・アルゴリズムの利用により、我々は「刺激(レコメンド)=反射(クリック)」からなる動物実験的な広告空間の中で常に何かに急かされ、かつては非商業的な時間だった友人や家族と過ごす時間さえも失いつつあるように思われる。スマートフォンの普及・発展で、2000年以降、人間の注意持続時間が、集中力がないことで知られる金魚のそれを下回ったとの研究結果もあるが、このような認知操作的な技術は、はたして人間の「尊厳」に配慮したものと言えるだろうか。
また近年は、アテンション・エコノミーが、誹謗中傷、偽誤情報の拡散・増幅や、エコーチェンバーなどによる政治的・社会的分断の構造的要因になっているのではないかとの指摘もある。このビジネスモデルでは、「反射」を得られる刺激的なコンテンツが経済的利益を生むが、憎悪や怒りに満ちた誹謗中傷や、ショッキングな偽誤情報は「刺激物」の典型だからである。さらに、アテンション・エコノミーにおいては、アテンションを長く引き付けておくことが経済的利益を生むため、アプリやコンテンツに「嵌まらせる」ための中毒的なUIやUXがもてはやされ、それがユーザーの精神的な健康に否定的な影響を与えるとの指摘もなされている。
本サブユニットでは、アテンション・エコノミーの社会的・政治的・経済的影響(個人の神経システムおよび精神構造への影響については「脳の仕組みと社会病理」サブユニットとのX)を領域横断的に分析し、その問題構造や課題を実証的に明らかにしていく。また、こうした実証的な分析・研究成果を踏まえつつ、アテンション・エコノミーの課題を克服するためのリテラシーのあり方、制度構築、技術設計なども検討する。
KGRIのプロジェクトでは、既に、この厄介なビジネスモデルを突き動かすための新しいコンセプトとして「情報的健康(informational health)」を掲げ、2度にわたり具体的な提言を行ってきた(https://www.kgri.keio.ac.jp/working-paper/2023.html)。このコンセプトは、アテンション・エコノミーの下でのレコメンダーシステム(アルゴリズム)により、私たちは情報の「偏食」が起きているのではないか、「作り手」や「産地」のわからない情報を「暴飲暴食」しているのではないか、こうした偏食や暴食が偽誤情報などに対する「免疫」を弱めているのではないかとの問題意識の下、「食育」とのアナロジーにより感覚的にリテラシーを高め、アテンション・エコノミーに対する市場の抑止力を高めていこうというもので、既に一定の広がりを見せている(参考URL:https://www.yomiuri.co.jp/topics/information-health/)。
本サブユニットでは、これまで実績を踏まえ、「情報的健康」のコンセプトをさらに発展させ、グローバルな連携の構築や、「情報的健康」を踏まえたレコメンダーシステムないしプラットフォームモデルの開発や展開といった社会実装を実現していきたい。
◆本サブユニットの活動実績(センター設立前)
・共同提言「健全な⾔論プラットフォームに向けて ver2.1―情報的健康を、実装へ」(2024年10月)
・KGRI主催シンポジウム「アテンションエコノミーの暗翳と『情報的健康』−総合知で創出する健全な言論空間」(2024年3月26日)
・共同提言「健全な⾔論プラットフォームに向けて ver2.0―情報的健康を、実装へ」(2023年5月)
・鳥海不二夫=山本龍彦『デジタル空間とどう向き合うか 情報的健康の実現をめざして』(日本経済新聞社、2022年7月)
・国際大学GLOCOM主催公開コロキウム「「情報的健康~健全な言論空間の実現に向けて~」(2022年3月23日)
・共同提言「健全な言論プラットフォームに向けて-デジタル・ダイエット宣言 ver.1.0」(2022年1月)
◆「情報的健康」関連の活動
・NHK財団「インフォメーション・ヘルスAWARD」
・読売新聞「偽情報 フィルターバブル エコーチェンバーにとらわれないために 「情報的健康」日米韓3か国調査 :あなたは「情報的健康」を知っていますか?」(2024年10月1日)
・NHK財団「インフォメーション・ヘルスを考える」(ステラnet)
・電通総研「情報摂取に関する意識と行動調査」
・読売新聞「特集:情報偏食」
◆「情報的健康」プロジェクトメンバーの活動(一部)
・鳥海不二夫「情報的健康の実現には食事や健康ドックの考え方が応用できる」(エモーショナルリンク合同会社、2024年11月22日)
・読売新聞「[情報偏食 ゆがむ認知]情報 漫然と信用…「情報的健康」日米韓3か国調査」(2024年03月26日)
・山本龍彦、クロサカタツヤほか座談会「生成AIは「おいしい毒リンゴ」―ほどよい距離を保ち、「AIのウソも嗤える」カルチャーを」(生活者データ・ドリブン・マーケティング通信、2024年2月2日)
・鳥海不二夫「「情報的健康」提唱者にYahoo!ニュースはどう映っているのか」(newsHACK、2023年8月18日)
・山本龍彦「情報的健康について―アテンション・エコノミーにどう向き合うか~第5回 デジタルTERA小屋 山本龍彦さん」(霞が関ナレッジスクエア、2023年5月26日)
・愛知県弁護士会主催シンポジウム「いつの間にか情報を偏食している私達~情報的健康を取り戻すには」(2023年2月18日)
・鳥海不二夫=山本龍彦「情報は食べ物に似ている なぜ「情報的健康」が必要なのか」(日経ビジネス、2022年8月17日)
・鳥海不二夫「健全な言論プラットフォームに向けた情報的健康の実現ダイジェスト版」(Yahoo!ニュース、2022年1月7日)
・鳥海不二夫「「情報的健康」目指す仕組みを データから社会を読む」(日本経済新聞、2021年12月30日)
◆メディア掲載
・毎日新聞「言論空間がおかしい」 SNS選挙巡り警鐘 経済同友会セミナー(2025年7月19日)
・NIKKEI Digital Governance「選挙をのみ込むアテンション、欲望の集積は民意か 慶大・山本教授」(2025年7月10日)
・読売新聞「SNS心身への影響議論 慶大でシンポジウム」(2025年7月3日)
・日テレNEWS 「それって本当?」情報も食べ物と一緒で摂取のバランスが大切? 憲法学と情報社会に詳しい慶応大学・山本龍彦教授に聞く(2025年6月11日)
・NHK「”情報的健康” 実現へ 鳥取県がプロジェクト発足」(2025年6月5日)
・生成AI 脅威の連鎖…「情報的健康」シンポジウム(2024年4月2日)
・読売新聞「「情報的健康」へデジタル・ダイエット宣言…[情報偏食]第1部<特別編>」 (2023年2月4日)
・読売新聞「「健全な言論プラットフォームに向けて――デジタル・ダイエット宣言」(第1版)要旨」(2023年2月4日)
MEMBER



慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート共同研究員
EU法、国際人権法
荒川 稜子
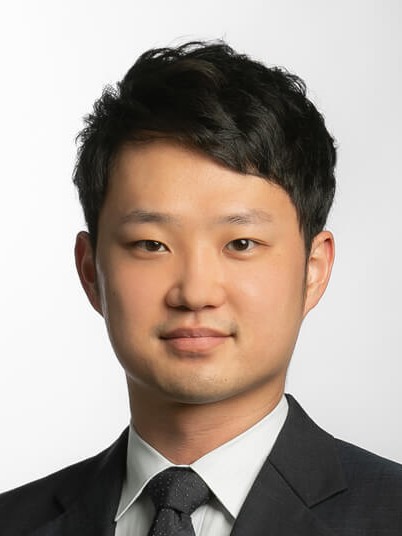

法学研究科 後期博士課程
慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート共同研究員
門谷 春輝




慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート共同研究員
鈴木 貴暁

慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート共同研究員
鈴木 雄也

森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 弁護士
慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート共同研究員
相馬 諒太郎


株式会社電通
消費者インサイト研究、未来予測、欲望(Desire)を基点としたマーケティング
千葉 貴志


株式会社日経BP総合研究所
公共・準公共分野とデジタル、取材・調査・編集
長倉 克枝
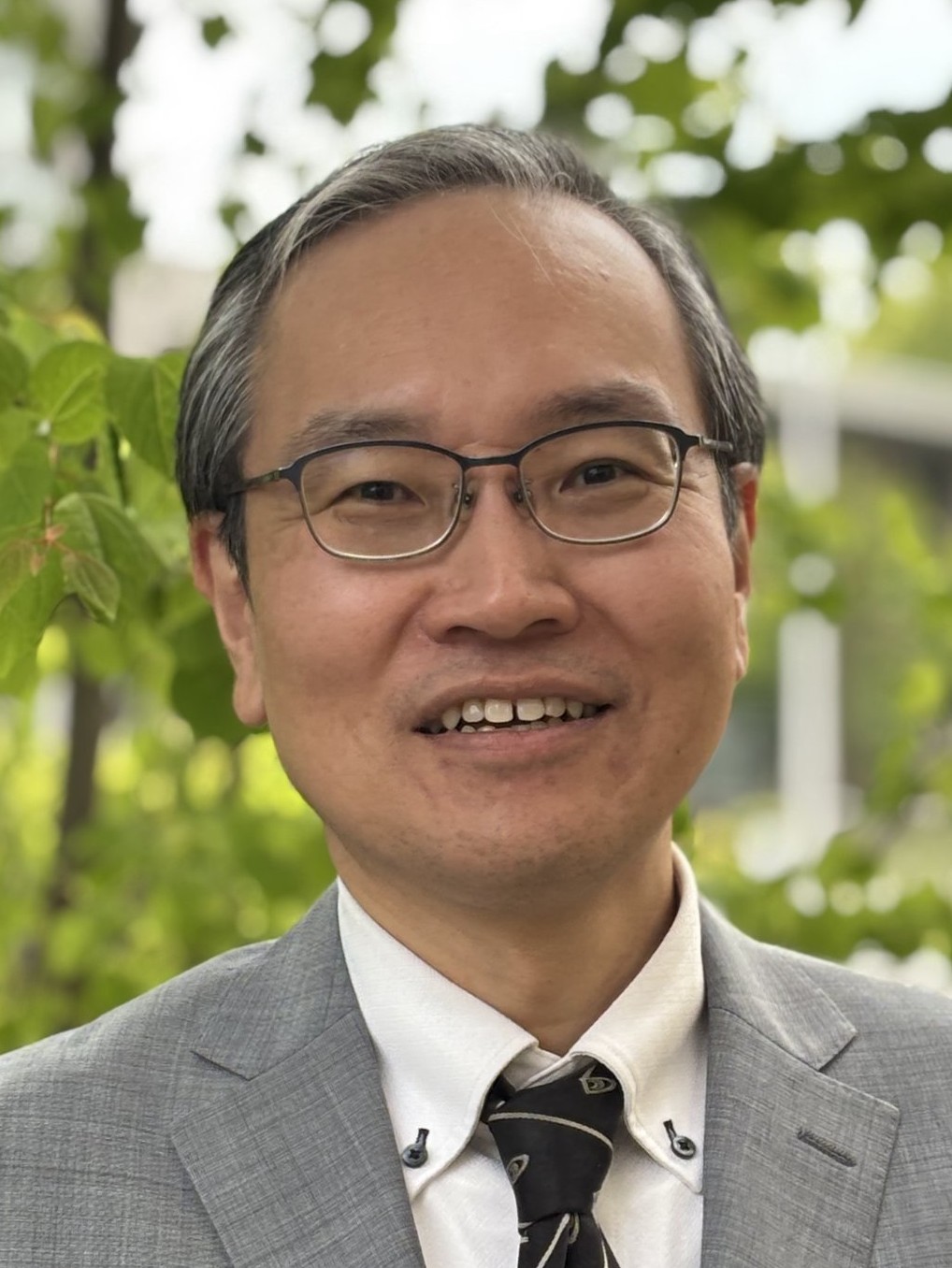
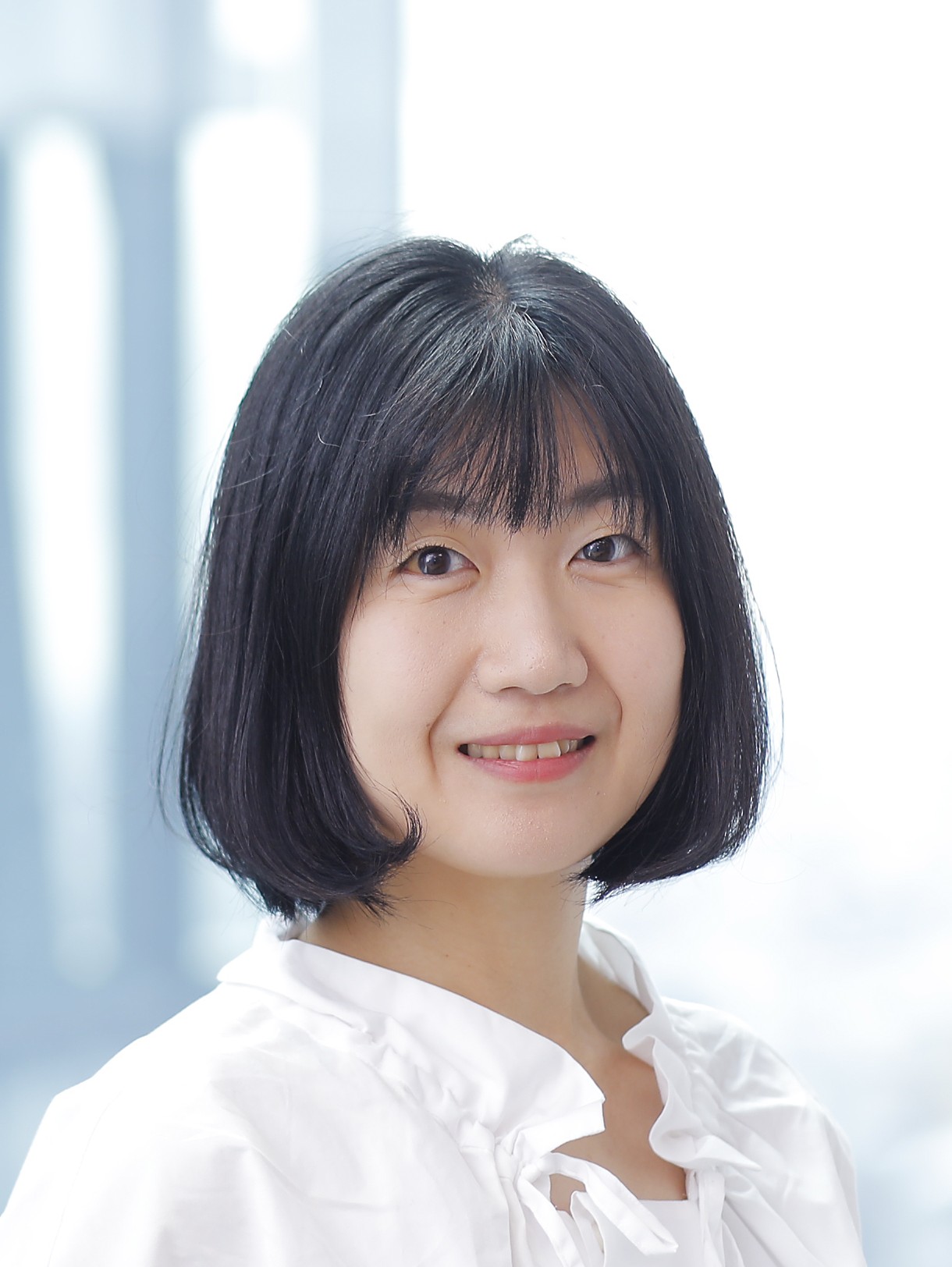
弁護士有資格者
慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート共同研究員
吹野 加奈


株式会社電通デジタル
慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート共同研究員
馬籠 太郎




